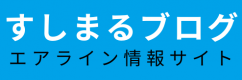エチオピア滞在4日目。
この日は人生で最も衝撃を覚えた日の一つです。
いつでも野生動物に襲われてもおかしくない荒野の中に集落を作って暮らす、ムルシ族の村を尋ねました。
その後、毎週火曜日に開催されるアルドゥバ市場を見学してから、トゥルミへ向かいます。

緑豊かなジンカからいっきに環境が変わる
標高約1,500メートルの山岳地帯に位置し、年間を通して雨量の多いジンカから、山を下り、西側に位置するマゴ国立公園へ向かいます。
緑の多い景色からたった車を1時間走らせるだけで、樹木が少ないサバンナ地帯へ変化。

途中、道路脇で、鷲が小鳥の巣を襲っている場面に遭遇しました。
野生は弱肉強食の世界ですね・・・


ずっと霧がかかっているジンカとは一変して、青空が広がる様になりました。



ムルシ族の集落へ行く同行人の数が半端無かったです(笑)。
アディスアベバからずっと同行してくれている通しガイドのアシューさんとドライバーのビルハンさんの他、地元の観光協会に登録されているアリ族のローカルガイドが同行し、更には散弾銃を持ったムルシ族出身のガードマン?までも車の中に乗ってきました。
もう車内はお祭り状態(笑)。

本当にな〜にも無い荒野の中に、ムルシ族の集落は現れます。
現代世界とのギャップに少し動揺
情報・通信技術が発達したこの世界で、ここまでも昔ながらの生活をしている人々に会えたのは恐らく人生で初めてです。
ただし、観光客は多く訪問するため、外国人には慣れていて貴重な収入源の一つでもあるので違和感はありません。


ムルシ族の人口は2万人弱で少数民族の中でも貴重な存在
人口1億人を超えたエチオピアの中で、ムルシ族は本当に少数です。
9割以上が、ここ南部のオモバレーに暮らしています。
家畜が貴重な支えとなり、季節に応じて各地を点在しながら暮らす遊牧民です。
独自の自然信仰の宗教や言語があり、公用語のアムハラ語とは語源が異なる。




どこの集落へ行っても子供達は興味津々ですぐに集まります。


↑オモバレー地域で飲まれている、コーヒー豆の殻を煎じたお湯。
ここ一帯はエチオピアの中で最も収入が低い地域の一つでもあり、コーヒー豆は高価なため、この様に本来であれば捨てる殻を煎じてコーヒー代わりとして飲まれています。




正直、外国人は僕一人だったので村に訪問して何を見学するば良いか動揺していたところ、通しガイドのアシューさんが写真撮影会をアレンジしてくれました。
ムルシ族と言えば、女性が唇にお皿をはめ込む習慣が有名。
女性が15歳ぐらいになると、唇を切り始め、まずは小枝から差し込んで慣らせる様ですが痛そうですよね・・・
この習慣の起源は、奴隷貿易が盛んだった時代に女性としての魅力を落とすためとも言われています。
現在は日常の生活ではこのリッププレートをはめていなく、観光客が来ると写真撮影のためにつけ始めます。

ところで、ムルシ族って皆全体的に背が高いんでよね〜
僕は身長166cmですが、女性だけでも軽く僕より上回っている人が多かったです↓

よく確認すると、唇だけでは無く、耳の部分もアクセサリーがはまるように切られています。


↑恐らく若い母親かなぁ。
幼い子供はお腹が膨れている場合が多かったです。
栄養失調の証拠でもあるので、あまり食べものはしっかり食べれていないのなぁ。
しっかり観光客から得る収入が皆の生活向上に結びついている事を願います。




男性は皆背が高い・・・軽く180cmぐらいはありそうです。

こちらが散弾銃を持ったムルシ族のガードマン。
少数民族訪問の中で唯一同行されたガードマンは正直謎でした。
国立公園内なので様々な猛獣がいるという事も関係していると思いますが、他の部族と争う事も稀では無い理由もあるかもしれません。
しかし、同じ少数民族でもジンカ周辺の肥沃な土地で農業をしているアリ族とは、極端に異なる生活スタイルをしていました。
車でたった1時間足らずの距離でもあるのに・・・
ひとまず、これからジンカへ戻り、昼食タイムにします。

エチオピアの「ユッケ」を食べて腹がやばい事になる
エチオピアには世界でも数少ない、生肉を食べる文化があります。
それは生の牛肉。
その昔、戦場において煙を焚いて敵に見つけられ無い様にするために、生肉を食べ始めたと言われています。
その名はキットフォ。

↑インジェラ(発酵したテフ粉のクレープでエチオピアの主食)の上には、ティブスと呼ばれるヤギ肉のステーキと、赤いのがキットフォです。
キットフォはもちろん鮮度が命。
大抵同日の朝にさばかれたのを食べるのでまぁ大丈夫だろうと思ってガイドとドライバーの食事をすこ〜しだけ分けてもらう事にしました。

一応殺菌効果として、唐辛子をたっぷりつけると良いらしいです。
辛いもの大好きなので問題はありませんでした。
ベルベレと呼ばれるエチオピアを代表するスパイスが既に含まれていて、このスパイスには唐辛子、コリアンダー(パクチー)、ニンニク、生姜が入っています。
臭みは無く、結構美味しく頂いたのですが・・・翌日から腹が完全にやられ、日本から持ってきた抗生物質を服用する羽目になりました・・・
今回は大衆食堂の様な場所で頂いたのが原因でした。
キットフォを食べるなら、アディスアベバの都会のしっかりしたレストランで食べる以外は避けた方が良いでしょう!
食後は本格的なエチオピアコーヒーを乳香の香りと一緒に楽しみます!
エチオピアではコーヒーの提供を妥協しません!!

ハマル族が多いアルドゥバ週市場へ移動
ジンカからトゥルミへの移動は山岳地帯。
標高1,000メートル以上の高原地帯を走るので日中もそこまで暑くなく、快適。

アルドゥバの市場に近づくと、見かける人々の様子が異なってくる事が伺えます。
バターと土を髪の毛に塗って独特な髪型をしています。
この地域に多く暮らすのはハマル族。
人口は60,000程度。



写真撮影は慎重に;ただだと思うな!!!
さて、オモバレーに来る観光客はもちろん、皆少数民族の写真を撮るために来ている様なもんですよね。
地元の人たちも理解しています。
明らかにローカルの人達よりも莫大な財産を持っている観光客に対して、写真撮影で儲けているのだろう!と思われるのも仕方が無い。
なので、市場の中でカメラを向けるとすぐに顔を隠すか険しい顔をします。
スマホカメラでも同様。
こんな忙しい市場の中でも皆さん反射神経凄い!

↑ほら、あえて意識して顔を隠するかそっぽ向いちゃうでしょ(これはスマホで撮影)。
ガイドから相場を聞いて被写体にしてくれる方へお支払いをしても、あまり笑顔をしてくれなかった・・・(笑)

でも、若いエネルギーある女性は喜んで応じてくれました。




今回、この他に後程ご紹介するもう1箇所の週市場を訪問しましたが、ここアルドゥバ市場程写真撮影に敏感ではありませんでした。
まとめ
ムルシ族の生活スタイルは強烈でした・・・現代社会とは掛け離れた過酷な地で暮らし、掟を守りながら生きている光景は本来ある人間の元気な源である「素」の部分が少し感じ取れた気がします。
また、同じ地域でも肥沃な土地に暮らすアリ族や、高原で気候にそこそこ恵まれているハマル族とは皆全く生活様式が異なるのも面白いです。
翌日は更にまたインパクトの強い部族の集落を訪れます。